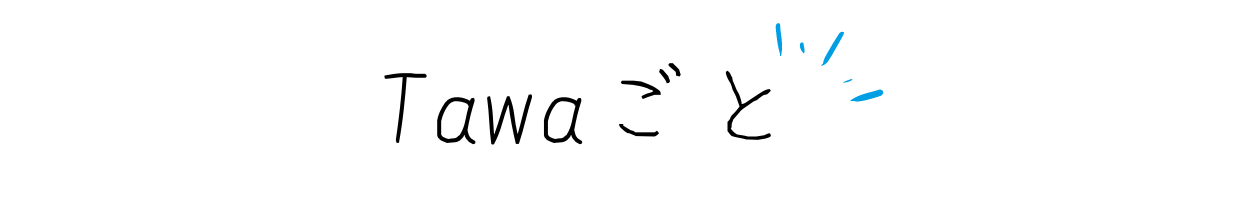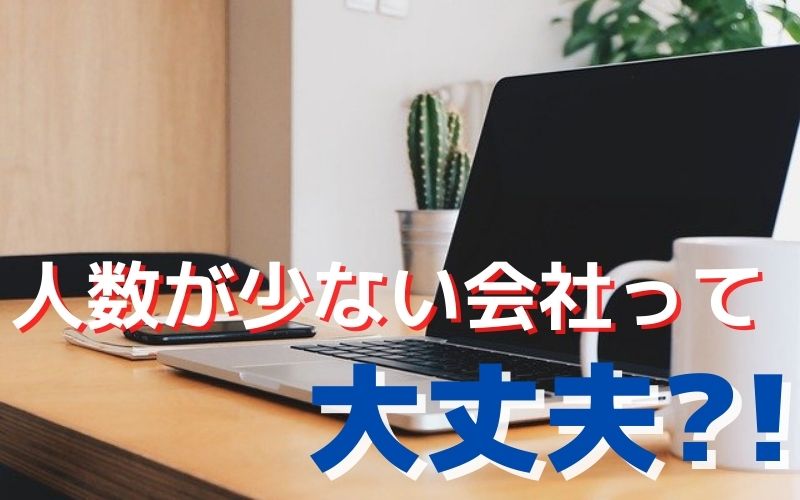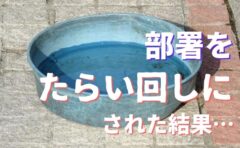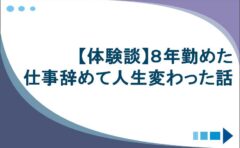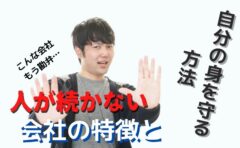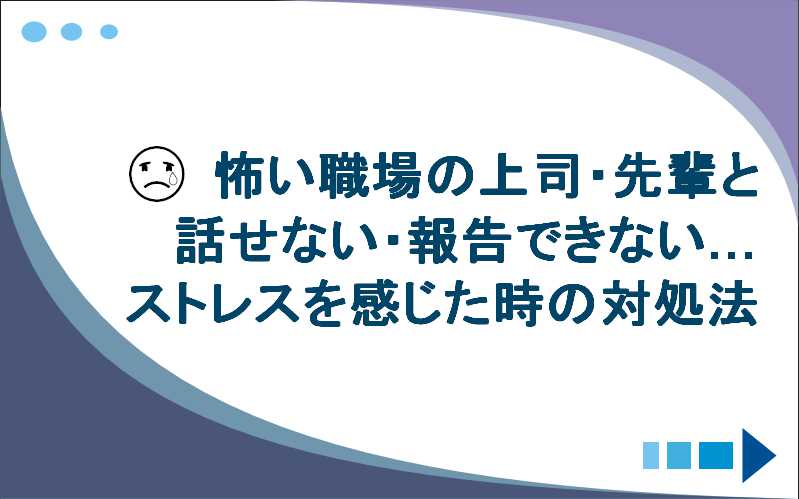こんにちは、Tawaです。
これから転職を考えてる人、転職活動真っ只中だって人で会社の規模が気になっている人へ。
- 社員はまともな人なんだろうか
- 仕事に安定性はあるだろうか
- 長く勤めることはできるだろうか
私は現在社員数20名程度の小さい会社に勤めています。そして入社前は私もこの辺りの事がかなり心配でした…。
どうせ勤めるんなら長く勤めたい。だから上手くやれるかどうかがすごく不安ですよね。
社員数900人規模の会社と20人規模の会社の両方を経験してきました。そんな経験から、大手と比べた小規模の会社のメリット・デメリットをお話しします。
もちろんこの記事の内容がすべての会社に当てはまるわけじゃないですが、1つの事例としてみてもらえればと思います。
メリット1:組織構成が単純だからフットワークが軽い
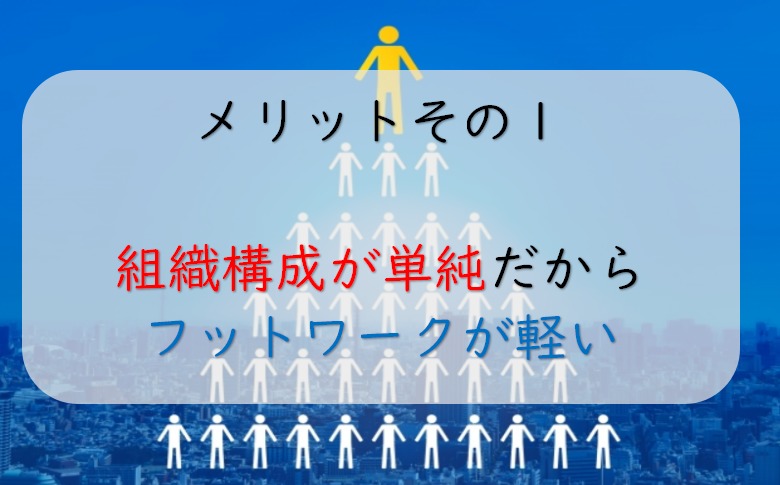
まずは1つ目のメリット。大手よりも組織構成が単純。なので仕事のフットワークが軽いんです。
これが個人的にはかなりありがたいと感じています。具体的にどういうことか、書いていきます。
組織構成が単純であることについて
まず、組織構成が単純であること。これはすぐにイメージできると思います。単純に人数の多さと組織構成の複雑さは比例関係にあります。
どれぐらい違うか。参考までに私の前職と現職の組織構成を比較してみます。
- 社長
- 役員(10人)
- 部(100~150人)
- 課(20~30人)
- チーム(4~6人)
- 課(20~30人)
- 部(100~150人)
- 役員(10人)
- 社長
- 部(4~5人)
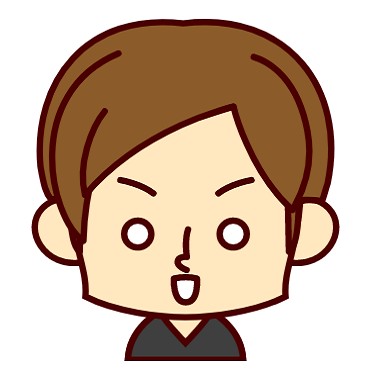
構成がちがいすぎるね・・・(笑)
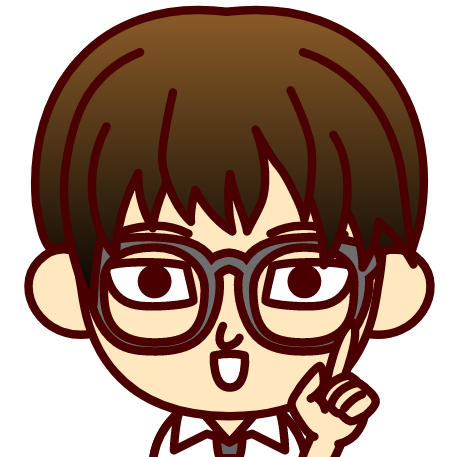
今の会社の方はすごく単純ですよね?
私もこの構成の違いにびっくりしました(笑)
この比較から組織構成に大きな違いがあるのは一目瞭然。これがフットワークの軽さにつながってきます。
フットワークが軽いことについて
ではフットワークが軽いというのはどういう事か。これはもう組織構成の違いからなんとなく分かると思います。
仕事というのは自分だけで完結するようなものはほとんどありません。書類やそのほかの成果物は上司や他部署に確認してもらう必要があります。
他にも自分の仕事を進めるために他部署の協力が必要不可欠になるケースも多いです。
当然ながら組織構成が複雑になればなるほど上司・他チーム・他部署が絡む仕事は複雑化していきます。
この組織構成の複雑さが、フットワークの重さに直結することはいうまでもなく。そしてフットワークの重さ=仕事のめんどくささと言ってもいいですよね。
このめんどくささが解消されことはかなり大きいです。
前の900人規模の会社では、書類1つ完成させるのにもすごく労力がいりました。リーダーに書類見せてダメ出し食らって直して、課長に書類見せてダメ出し食らって直して…。
思い出しただけでうんざりしますが。
それに比べて今の20人規模の会社は、上司と関係者に書類をメールして、指摘もらったら直してそれで終わり。
もう気軽さが段違いです。
メリット2:人数少ないから人間関係が楽
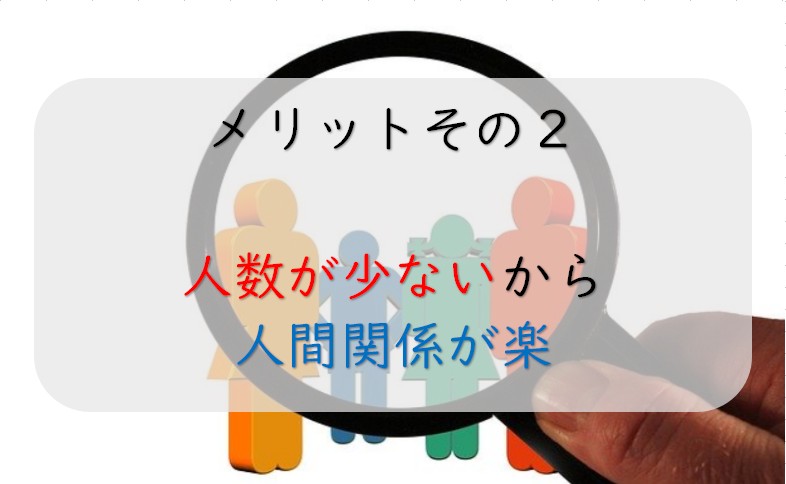
2つ目のメリットは、人数の少なさによる人間関係の単純さ。
大企業の場合、1つの仕事を進めていくにも多くの部署や人がかかわってきます。そして部署間・社員感には必ず利害というものが存在します。
この利害の衝突にしょっちゅう遭遇することになります。あちらを立てればこちらが立たず。私はこの利害の衝突にしょっちゅう悩まされてきました。
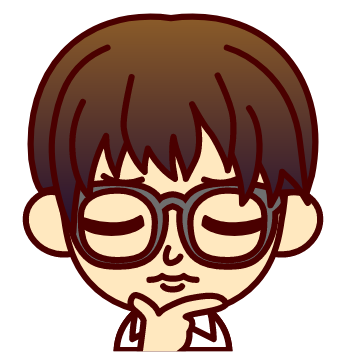
基本的に自分や自部署の事しか考えない人が多かったのでこれもうんざりでした・・・。
人数が少なければ非常に単純。人間関係は仕事をするうえで良くも悪くも重要ですよね。
ここが良好でない事にはどんなに魅力的な収入・仕事であろうと台無しです。あなたも今現在悩まされてはいませんか?
人数が少なければそうした煩わしさから解放されます。
特に大企業での人間関係につかれた。と感じている人には魅力的です。
自身も他の人や他部署を思いやる意識が必要
人間関係が楽と言っても、それを作り上げていくのは社員一人一人。
それぞれが他部署を思いやる意識が必要です。
大企業の感覚で言うと、小規模の会社は1つの部署のようなもの。皆が同じ方向を向いて会社を運営していく事が必要という事ですね。
デメリット1:人間関係はデメリットにもなりうる・・
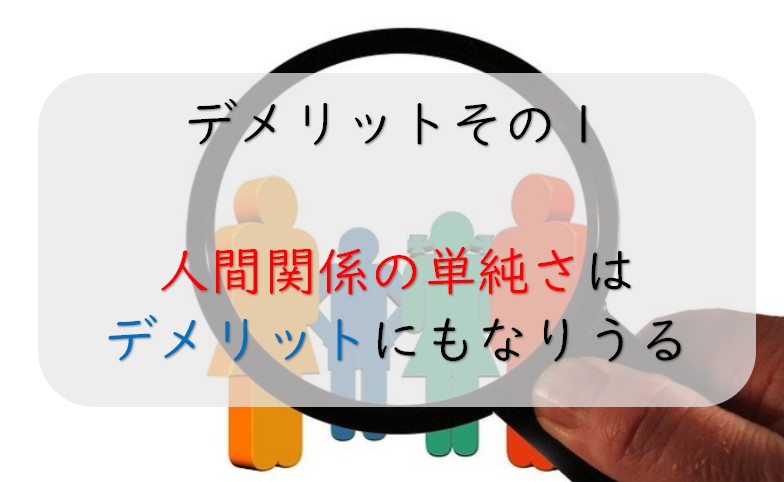
さてここからはデメリットのおはなし。
メリットで「人間関係の単純さ」を挙げました。ですがこれはデメリットにもなります。
社内で逃げる手段がとりにくい
人間関係が単純が故に、その会社にそりの合わない人がいた場合が厄介。会社内で「逃げる」という事ができなくなるんですね。
大企業だったら他部署に逃げて関りを避ける方法もあります。
しかし小規模の企業ではどうしても関係が密になりますので、そうもいきません。
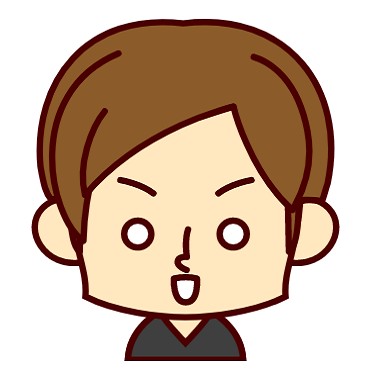
逃げる手段として「部署異動」っていう手が使えないという事か。
それはつらいね・・・。
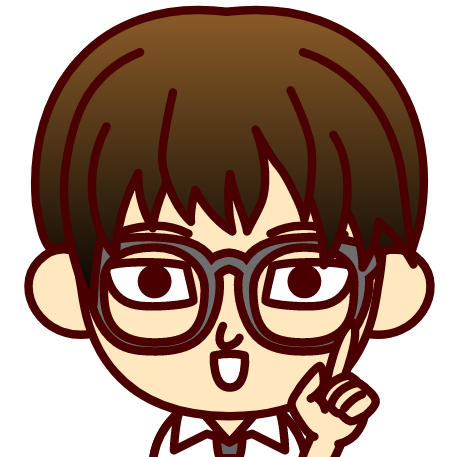
そうなんです・・・。人によっては苦痛で仕方ないでしょうね・・。
私の事務所は現在4人。幸いなことにいい人間関係を築けてます。(他の支店、本社には癖の強い人も何人かいますが・・・)
しかしながら人間関係が原因で辞めていった人もいます。
私はこんな働きやすい会社ないのにもったいないなと思うのですが、そこはやはり人によって合う、合わないの違いは出てくるので仕方ありません。
人がいる以上、どうしても人間関係のこじれというものは出てきてしまいます。
もうこれは組織の大小関わらず。
ここはある意味運の要素が強いです。が、人間関係はデメリットにもなりえてしまうという事になります。
事例:メンタルがあまりにも弱かった人
私が入社して大体一か月後、一人の人(女性)が会社を辞めていきました。当時勤めていたとある我の強い人とどうしてもそりが合わなかったそうです。
その人はメンタルが非常に弱かったとも聞いています。今一緒に働いている人いわく、良く会社の外で悩み相談をされていたそうで。
事例:我があまりにも強かった人
そのメンタルがあまりにも弱かった人を追いやってしまった我が強い人ですが、こちらも辞めていきました…。
どうやらこの人のせいで、今までも何人か会社を辞めていったようです。
もうこれ以上許容できないという事で会社として対処に乗り出しました。
会社でとある状況の変化が起こった際にその人に対して転勤の指示を出したのです。家庭の事情から、その人が転勤を受け入れられないのは承知の上で。
転勤の指示があった場合は指示に従わなければいけないことは就業規則に記載があります。それを利用したわけですね。
結局その人は会社の思惑通りに転勤を受け入れず辞めていくことになりました。
その会社の社風とか人間性に関しては面接の時にしっかり観察!
人間関係、こればっかりは運なのでどうしようもない…。でも人間関係のこじれってなるべく避けたいですよね。
私もそういうのは大嫌いで、前の会社では悩まされまくってきたのでそれはめちゃくちゃ分かります!!
なので、もしあなたが人数が少ない会社の求人に興味があるんなら、
- 会社の雰囲気
- 社員の雰囲気
この辺りをよく観察するようにしてください。
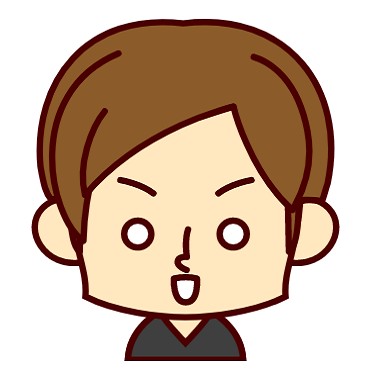
雰囲気っていっても具体的にどんなところ見ればいいの?
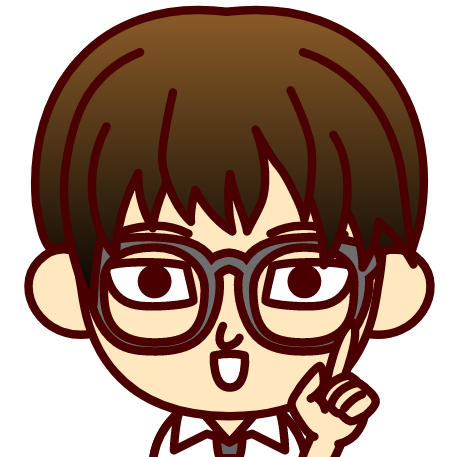
年齢層・男女比率・面接担当してくれた人の性格・会社自体は体育会系かまったり系か。
自分がその会社に勤めていることをイメージしながら考えてみるといいですよ。
デメリット2:部署が不向きだった時、部署異動が難しい
上で「社内で逃げる手段がとりにくい」ということに触れましたが、これは自分が配属された部署が不向きだった時にも言えます。
大きい規模の会社なら部署異動などの手段で何とか対処できるケースが多いです。ですが小規模な会社ではそうはいきません。
部署の数もそんなに多くないし、殆どの部署は人で埋まっているからです。
このように部署が不向きというミスマッチが起こってしまった場合、その会社で働き続けることが致命的になってしまう可能性が高いです。
事例:40歳超えて未経験で採用された営業職の人の末路
私が入社した当初、丁度1年経ったぐらいの営業職の方が1人いました。
40歳を超えて営業として入社されたのですが営業は前職まで未経験とのこと。とても穏やかな感じの人でああ、この人とだったら一緒に仕事していけるなと思っていたのですが。
ただ穏やかでありつつも引っ込み思案なところがありました。
営業と言えばある程度トークスキルが要求される職種ですよね。(それがなくてもうまくやれる人も いるようですが)
その引っ込み思案な性格が故にトークスキルが乏しく、営業に向いていなかったわけです。
さらに年齢も40歳を超えています。
会社としてもこれ以上育てても華が咲くことはないだろうとあきらめモードへ。半ば見捨てられたような形になってしまいました。
他部署に異動という手段も取れず、結局その人は会社に居づらくなって自ら身を引くことに・・・。
デメリット3:自分の担当範囲外の仕事をやることもある
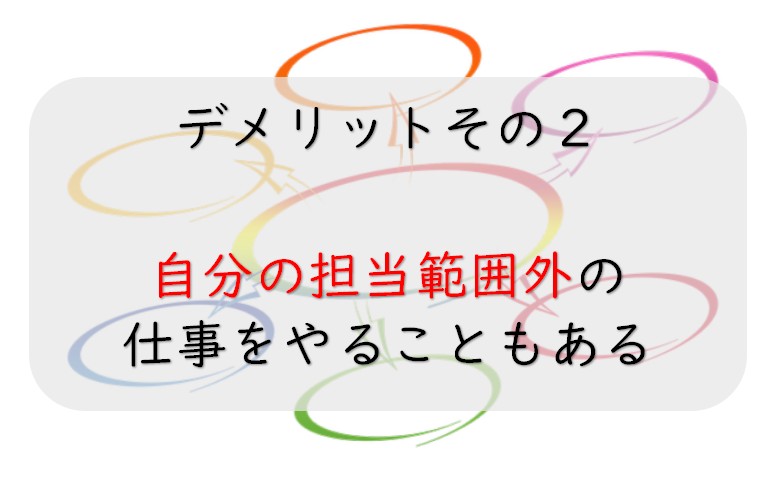
3つ目のデメリットは、自分の担当範囲外の仕事も手広くやらなきゃいけない可能性があること。
どういうことか?人数が少ないという事は、すなわちリソースが少ないという事です。
リソースの少なさ故、突発的に他部署や自分の担当範囲外のヘルプをやることもあるかもしれません。
この辺りは単純にあなたが受け入れられるかどうかという問題にはなってるのですが。
協調性の問題ですね。
もしあなたが「なんで自分の職務以外の事もやらなきゃいけないの?」という考えを持ってる場合。
小さい会社はちょっと向いてないかも?!
ある程度は軟性持って仕事することが必要です。
その他
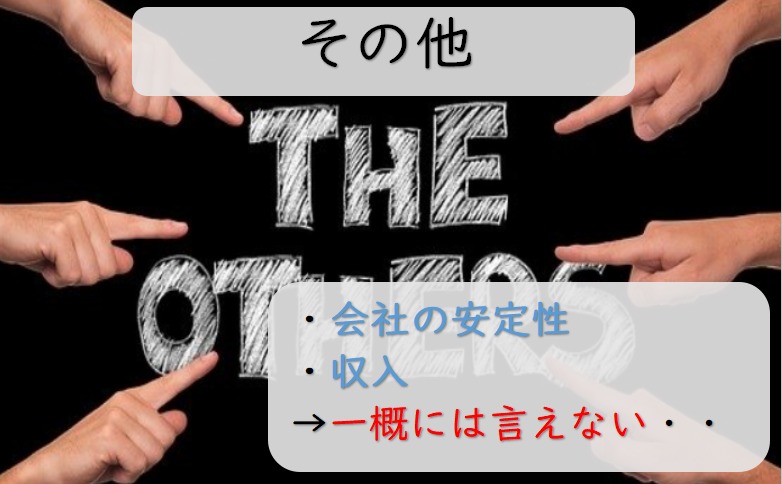
メリット・デメリットを明確に分けづらい2点をお話しします。
会社の安定性
人数が少ないと会社の安定性って面も気になりますよね。
ただ残念ながらこれは会社によるので明確な回答はできません。業績的に怪しい大企業もあります。逆に右肩上がりの中小企業もあります。
会社の規模と安定性は比例関係にありません。
安定性を測る1つの指標に「自己資本比率」があります。この比率が高い企業トップ5が以下の通りです。
| 企業名 | 自己資本比率(2020年3月期) |
|---|---|
| ツツミ | 97.9% |
| ナノキャリア | 97.0% |
| テクノマセマ | 96.9% |
| HEROZ | 96.5% |
| キーエンス | 95.8% |
キーエンスは比較的有名なのでご存じかと思います。でも他の4つの企業は耳にしたこともないですよね。
一方で大手の企業を適当にピックアップしてみると、
大手企業の自己資本比率
| 企業名 | 自己資本比率(2020年3月期) |
|---|---|
| 日立製作所 | 31.8% |
| トヨタ自動車 | 38.2% |
| イオン | 9.60%(2020年2月期) |
| 富士通 | 38.9% |
上の上位5社と比べて思いのほか低いことに驚きます。
もちろん安定性を測る指標や要因は自己資本比率だけではないでしょう。
しかし大手だからと言って安定していると考えるのは早計という事もお分かりかと思います。
2020年はコロナ禍の真っ最中。
ばたばたと力のない会社は淘汰されていくかも知れません。
収入
あなたも気にしているであろう収入。
こちらも残念ながら明確な回答はできません。
ただ、上の安定性と違って企業の規模とはある程度の比例関係があります。
| 企業規模 | 男性(万円) | 女性(万円) | 計(平均)(万円) |
| ~9人 | 424 | 247 | 340 |
| 10~29人 | 497 | 280 | 404 |
| 30~99人 | 495 | 296 | 413 |
| 100~499人 | 522 | 313 | 437 |
| 500~999人 | 580 | 337 | 479 |
| 1,000~4,999人 | 632 | 323 | 501 |
| 5,000人~ | 687 | 291 | 516 |
このように比例関係にはあるものの、実際のところは求人に記載されている想定年収を参考にしながら情報を集める必要があります。
ちなみに私に関して言うと、小規模の会社に転職はしたものの年収はアップしています。
全員で4人の職場の実態について
私の会社は全員で20人程度です。
そして私の事務所のメンバーは全員で4人と超少人数。そんな私が事務所の職場について語ります。
事務所で1日中一人ボッチなこともしばしば
人数が4人しかいないから、事務所で1日中ボッチになることもしばしば。自分の仕事をこなしつつ電話番をする感じです。
もちろんにぎやかなのもそれはそれで悪くないのですが、一人で過ごすことも好きな私にとってはこんな状況も全然OK。
休憩中にYoutube見ようが音楽聞こうが何にも問題ありません。
人間関係は良好
上にも少し書きましたが、人間関係は良好です。
ベテランの50代の人が一人いますが、特にふんぞり返っているわけでもなくフランクな感じです。
時々「一杯飲んでく?」みたいな感じでよく一緒に飲みに行ってます。
(おかげさまで良くも悪くも酒を飲む習慣ができてしまったわけですが・・・)
入社前は人間関係が大丈夫か心配していましたが、気軽に仕事終わりに飲みに行けるような、そんな感じでほんとによかったと思います。
眠くなったら立ってウロウロしても気にされない
事務所は4人しかいない割りにそれなりの広さがあります。後もう4人ぐらい入ってもまだまだ全然余裕があるぐらいです。
だからそこら辺をうろついても別に怒られることもないし、気にされることもありません。
昼休憩後って大体眠くなりますけど、そんな時に立って気軽にリフレッシュできるのはありがたいですね。
まとめ
少人数の会社について
- メリット
- 組織構成が単純だからフットワークが軽い
- 人数少ないから人間関係が楽
- デメリット
- 人間関係はデメリットにもなりうる・・
- 部署が不向きだった時、部署異動が難しい
- 自分の担当範囲外の仕事をやることもある
- 明確に分けづらい点
- 会社の安定性
- 収入
人数の多い会社少ない会社様々ですが、合う合わないは人それぞれ。
ここに挙げたメリット・デメリットを参考にしてください。そしてあなたにとってベストな会社を見つけることができるように応援してますよ!